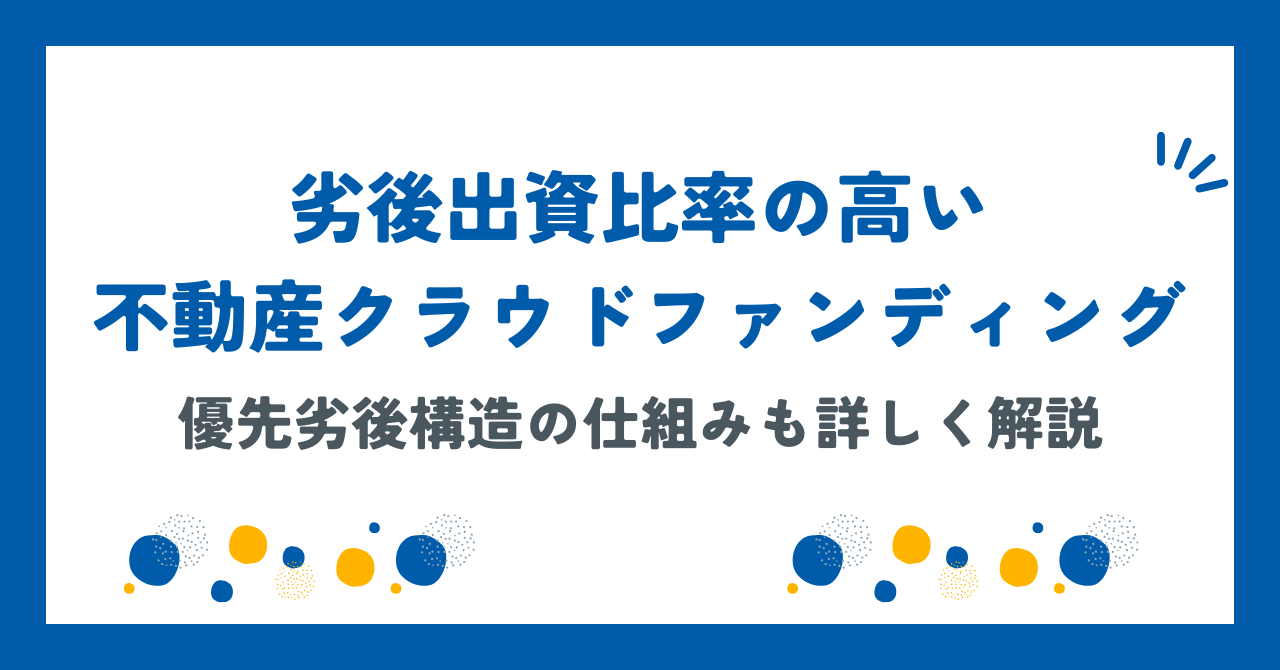不動産クラウドファンディングには「優先劣後構造」と呼ばれる仕組みがあり、投資家の元本保護に役立っています。
「優先劣後構造」とは、事業者が自己資金を劣後出資として一定割合を出すことで、損失が発生した際にまずはその分がカバーされ、投資家のリスクを減らす重要な仕組みです。
劣後出資比率が高いほど、投資家にとって元本割れリスクが低くなり、安心して投資をしやすくなるメリットがありますが、比率の設定はサービスにより大きく異なります。
本記事では、「優先劣後構造」の仕組みを詳しく解説すると共に、劣後出資比率が高いと評判の不動産クラウドファンディングサービスを8選ご紹介します。
サービスごとの劣後出資比率の水準や特徴も比較しながら解説するので、ぜひ参考にしてみて下さい。
劣後出資比率が20%以上と高い不動産クラウドファンディング
| 不動産クラファン | 劣後出資比率 | 平均利回り | 累計ファンド数 |
|---|---|---|---|
| らくたま | 平均40% | 5〜6% +アップサイド配当 | 27件 |
| Rimple | 一律30% | 2.7〜4.0% | 104件 |
| ちょこっと不動産 | 平均39% | 4% | 39件 |
| iRD | 平均51% | 3.6〜5.6% | 16件 |
| おうちの再生ファンドVIFA | 平均32.1% | 13.87% | 9件 |
| KORYO Funding | 28% | 4.5〜4.8% | 23件 |
| みらファン | 平均23% | 5.5〜8.0% | 19件 |
| property+ | 4〜70%まで幅広い | 3.0〜10% | 33件 |
| えんfunding | 平均20% | 4〜6%が中心 | 43件 |
らくたまの劣後出資比率は平均40%

| 劣後出資比率 | 平均40%。50%の案件もあり |
|---|---|
| 最低投資金額 | 1万円 |
| 運用期間 | 3ヶ月〜1年の案件が中心 |
| 累計募集実績数 | 27件 |
| 元本割れ・分配遅延 | 0件(償還遅延ゼロ宣言) |
| 平均利回り | 5〜6% |
らくたまは、劣後出資比率が平均40%とかなり高く、なかには劣後出資比率50%の案件まである不動産クラウドファンディングです。
過去の元本割れや償還遅延は0件で、償還遅延ゼロ宣言を出しており、今後も予定通りに償還することに強くコミットメントしているサービスです。
年利回りは5〜6%の案件が多く、一般的な不動産クラウドファンディングと同程度の水準となっています。
しかし、らくたまは早期償還されることが多く、その場合でも、元々の全期間分の配当金額がもらえるため、実質利回りがアップします。
たとえば、元々1年間の予定の案件が6ヶ月で早期償還された場合でも、1年分の配当がもらえるため、利回りは2倍になります。
そのほかにもマスターリース契約でリスクを軽減させたりなど、守りも攻めも強い不動産クラウドファンディングとして注目を集めています。
劣後出資比率の高い案件でリスクを抑えつつ、利回りもなるべく上振れを目指したいという方に最もおすすめのサービスです。
翌日償還・アップサイド配当で実質利回りアップ
らくたまに無料登録して案件をみるRimpleの劣後出資比率はすべて一律30%
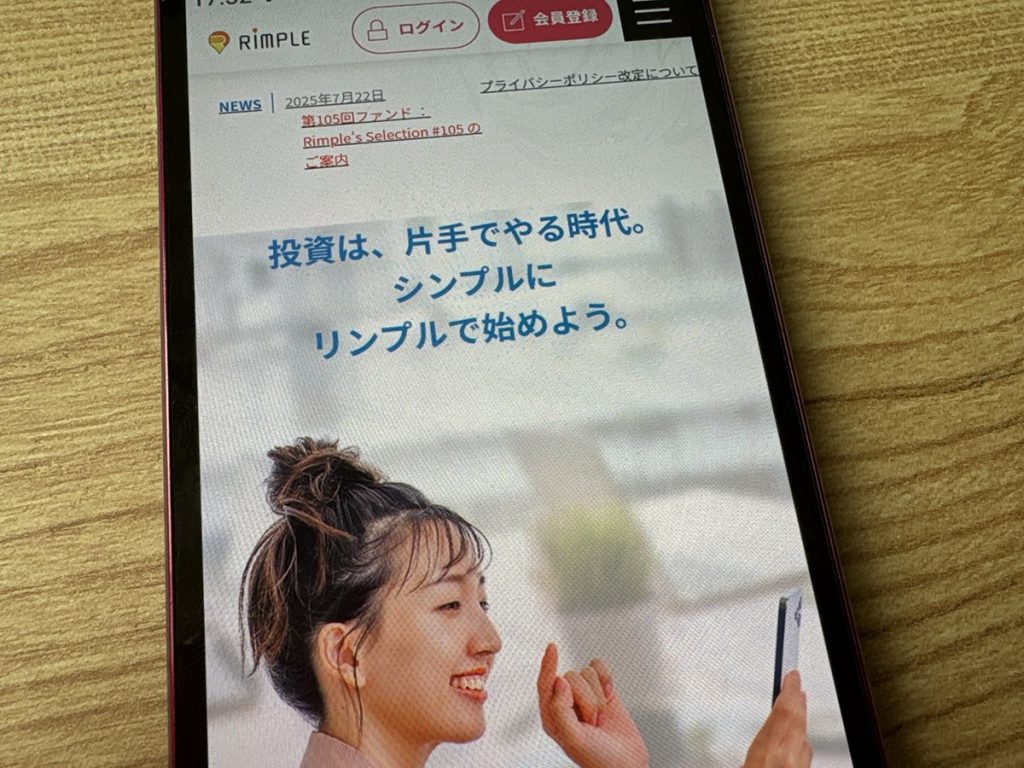
| 運営会社 | プロパティエージェント株式会社 |
|---|---|
| 劣後出資比率 | 一律30% |
| 最低投資金額 | 1万円 |
| 累計募集実績数 | 104件(2025年7月時点) |
| 元本割れ・分配遅延 | 0件 |
| 平均利回り | 2.7%〜4% |
Rimpleは、東証プライム上場企業「ミガロホールディングス」のグループ会社である「プロパティエージェント株式会社」が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
これまで元本割れ実績はなく、高い信頼性を持つほか、独自のポイント制度「リアルエステートコイン」を導入しています。
Rimpleの組成ファンド数は現時点で104件と豊富なことに加え、全てのファンドで劣後出資比率を一律30%に設定しているのが大きな特徴です。
多くの不動産クラウドファンディングサービスでは、案件ごとに出資比率が異なるのが一般的のため、Rimpleのように全案件を一律で高い水準を維持しているのは非常に珍しいポイント。
上場企業グループが運営しているという企業の信頼性に加え、リスクを抑えて安定的に資産運用をしたい方に特におすすめのサービスです。
利回りは控えめですが、最低投資額1万円でできる手軽さと、劣後出資割合が一律という点で、リスクを抑えたい投資家にとっては魅力的なサービスと言えるでしょう。
\ 1万円から!ポイント利用も可 /
【無料】Rimpleの会員登録をするちょこっと不動産の劣後出資比率は平均39%
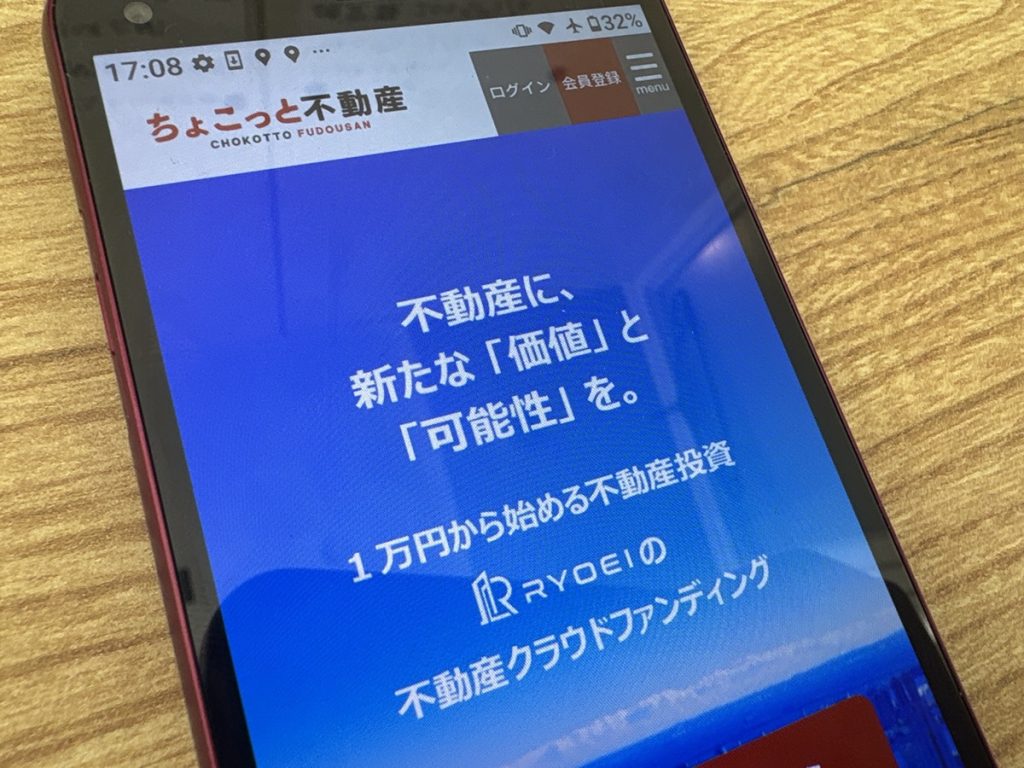
| 運営会社 | 株式会社良栄 |
|---|---|
| 劣後出資比率 | 平均39% |
| 最低投資金額 | 1万円 |
| 累計募集実績数 | 39件 |
| 元本割れ・分配遅延 | 0件 |
| 平均利回り | 4%前後 |
ちょこっと不動産は、1991年創業の「株式会社良栄」が運営する不動産クラウドファンディングで、2021年よりサービスを開始しています。
戸建てやマンションの開発から販売、賃貸まで一貫して手がけており、物件選定や管理も自社で行う体制が特徴です。
自社開発の建売戸建てシリーズ「Buena Town」など、安定した収益が見込める案件も提供しています。
一部のファンドではマスターリース契約を導入することで、家賃収入の安定性も確保しているのも特徴です。
劣後出資比率は平均39%と高めに設定されており、投資家のリスクを抑える構造が特徴です。
中でも2024年に募集開始された「杉並区宮前プロジェクト最終章」では、自社過去最高となる劣後出資割合67%が設定され、安全性を重視した取り組みが話題となりました。
実績ある企業による運営に加え、高い劣後出資比率を安定して維持している点が魅力的なサービスと言えるでしょう。
iRDの劣後出資比率は平均51%
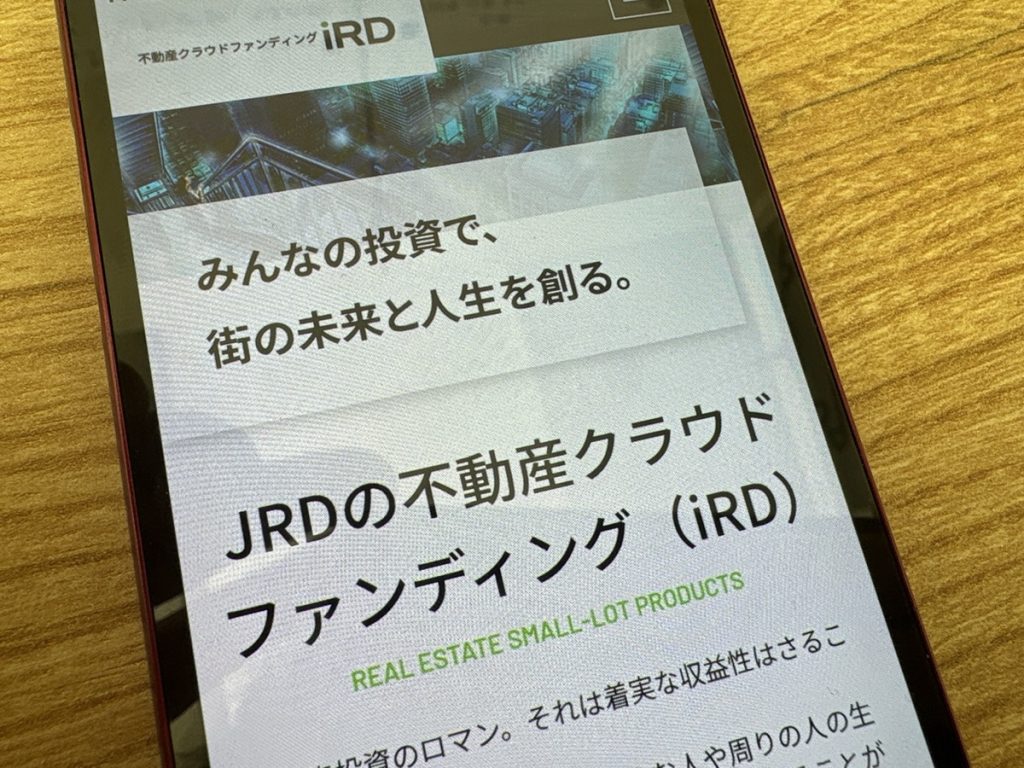
| 運営会社 | JRD株式会社 |
|---|---|
| 劣後出資比率 | 40〜50% |
| 最低投資金額 | 10万円 |
| 累計募集実績数 | 16件 |
| 元本割れ・分配遅延 | 0件 |
| 平均利回り | 3.6〜5.6% |
iRDは、安全性と利便性、収益性の三拍子が揃っている不動産クラウドファンディングサービスです。
投資対象は、東京23区内・駅徒歩10分以内という利便性の高い立地に限定されており、自社開発の高品質マンション「セジョリシリーズ」を中心に展開しています。
安定した賃貸需要と高い資産価値が期待できる物件に投資できます。
iRDの大きな特徴は、劣後出資比率を原則40〜50%前後と業界トップクラスの水準で設定している点です。
万一の損失が発生した場合でも、まずは運営会社の出資分から優先的に損失が吸収されるため、投資家の元本毀損リスクを最低限に抑えています。
また、全物件にJRDグループとのサブリース契約が付帯しており、空室や家賃滞納といった運用上のリスクにも対応しています。
最低投資額は10万円ですが、運用期間は3〜6ヶ月と短期運用型のファンドが多く、リスクを抑えて始めやすい点も大きな魅力です。
おうちの再生ファンドVIFAの劣後出資比率は平均32.1%
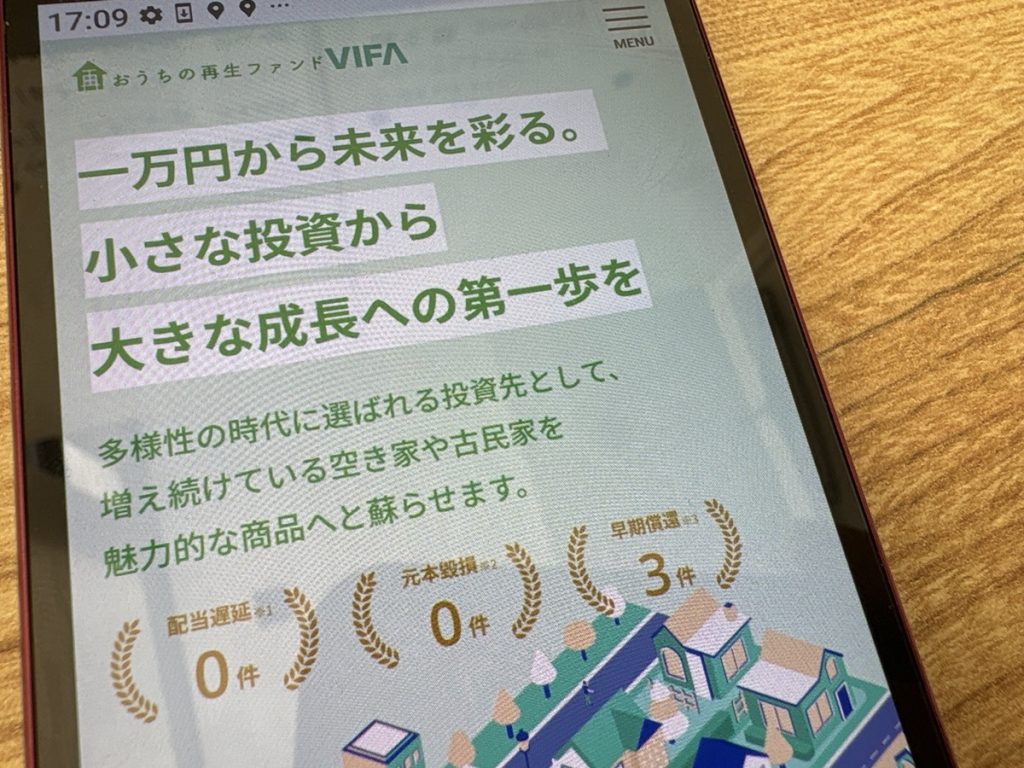
| 運営会社 | レクストアセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 劣後出資比率 | 平均32.1% |
| 最低投資金額 | 1万円 |
| 累計募集実績数 | 9件 |
| 元本割れ・分配遅延 | 0件 |
| 平均利回り | 13.87% |
おうちの再生ファンドVIFAは、空き家や古民家を魅力ある収益資産として再生し、投資家に提供する不動産クラウドファンディングサービスです。
運営会社の設立は2020年、サービス開始は2024年5月とまだ新しいため、組成ファンド数は9件と控えめですが、劣後出資比率と利回りの高さが大きな魅力です。
参考までに、これまで公開された全9件のファンドを集計すると、劣後出資比率の平均は32.1%、利回りの平均は13.87%と、いずれも業界水準を上回る数値でした。
| ファンド名 | 劣後出資比率 | 利回り | 運用期間 |
|---|---|---|---|
| おうちの再生ファンドVIFA1号 | 49% | 12.0% | 3ヶ月 |
| おうちの再生ファンドVIFA2号 | 48% | 12.0% | 3ヶ月 |
| おうちの再生ファンドVIFA3号 | 68% | 21.3% | 2ヶ月 |
| おうちの再生ファンドVIFA4号 | 20% | 12.0% | 3ヶ月 |
| おうちの再生ファンドVIFA5号 | 22% | 12.0% | 3ヶ月 |
| おうちの再生ファンドVIFA6号 | 20% | 12.0% | 3ヶ月 |
| おうちの再生ファンドVIFA7号 | 22% | 24.0% | 1ヶ月 |
| おうちの再生ファンドVIFA8号 | 20% | 12.0% | 3ヶ月 |
| おうちの再生ファンドVIFA9号 | 20% | 7.5% | 9ヶ月 |
なお、運用期間は3ヶ月前後の短期が中心で、最高24%の高利回り案件もあるため、リスクを抑えつつ高リターンを狙いたい投資家におすすめのサービスと言えます。
KORYO Fundingの劣後出資比率は平均28%
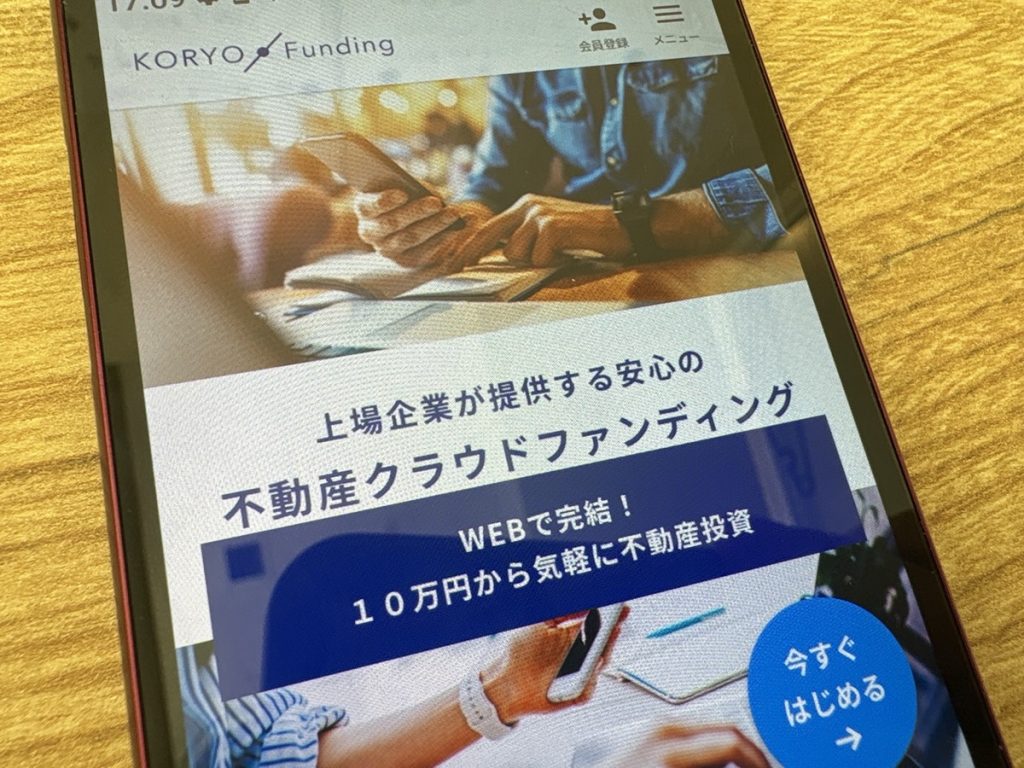
| 運営会社 | 香陵住販株式会社 |
|---|---|
| 劣後出資比率 | 平均28% |
| 最低投資金額 | 10万円 |
| 累計募集実績数 | 23件 |
| 元本割れ・分配遅延 | 0件 |
| 平均利回り | 4.5〜4.8% |
KORYO Fundingの運営会社は1981年創業・東証スタンダード上場の「香陵住販株式会社」が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
上場企業ならではの信頼性と安定性の高さが魅力で、不動産クラウドファンディングは2022年にサービス開始しています。
茨城県を起点とし、東京・千葉エリアの賃料物件を対象としたインカム型ファンドを中心に展開しています。
地域密着型の運用方針により、地元の情報に精通した堅実なファンド組成が大きな強みです。
劣後出資比率は20〜30%に設定されている案件が多く、過去には40%といった高水準のファンド実績もあります。
賃料収入をベースにした1年未満の短期ファンドが中心で、利回りは4.5〜4.8%程度が多く、安定型重視の投資家におすすめのサービスと言えるでしょう。
みらファンの劣後出資比率は平均23%
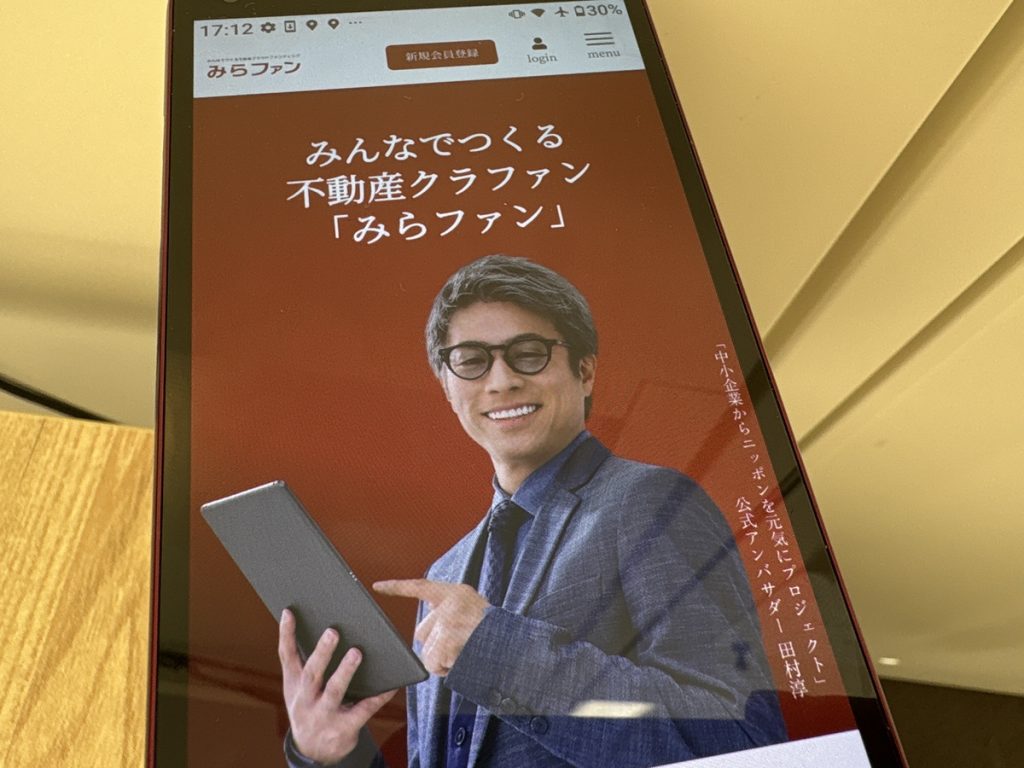
| 運営会社 | 株式会社みらいアセット |
|---|---|
| 劣後出資比率 | 平均23% |
| 最低投資金額 | 1万円 |
| 累計募集実績数 | 19件 |
| 元本割れ・分配遅延 | 0件 |
| 平均利回り | 5.5〜8.0% |
みらファンは、名古屋エリアに強みを持つ不動産クラウドファンディングサービスで、地域密着型の物件運用に強みを持っています。
地域性を活かした物件選定と運用力が大きな魅力です。
また、『中小企業からニッポンを元気にプロジェクト』への参画や、SDGs協会による「SDGs事業認定」の取得など、社会的責任やサスティナビリティを重視した取り組みにも力を入れています。
取り扱う物件は、居住用や商業用、ホテルなど多岐にわたり、分散投資がしやすい点も投資家にとってのメリットです。
ファンドの運用期間は3〜12ヶ月の短期型が中心で、劣後出資比率は20%以上と、一定の安全性も確保されています。
社会貢献性と投資効率の両立を目指し、少額から手軽に始められる点も魅力で、初心者から経験者まで幅広い層におすすめできるサービスです。
年利が5.5%~8.0%と高い
【無料】みらファン公式サイトで登録するproperty+の劣後出資比率は平均20%
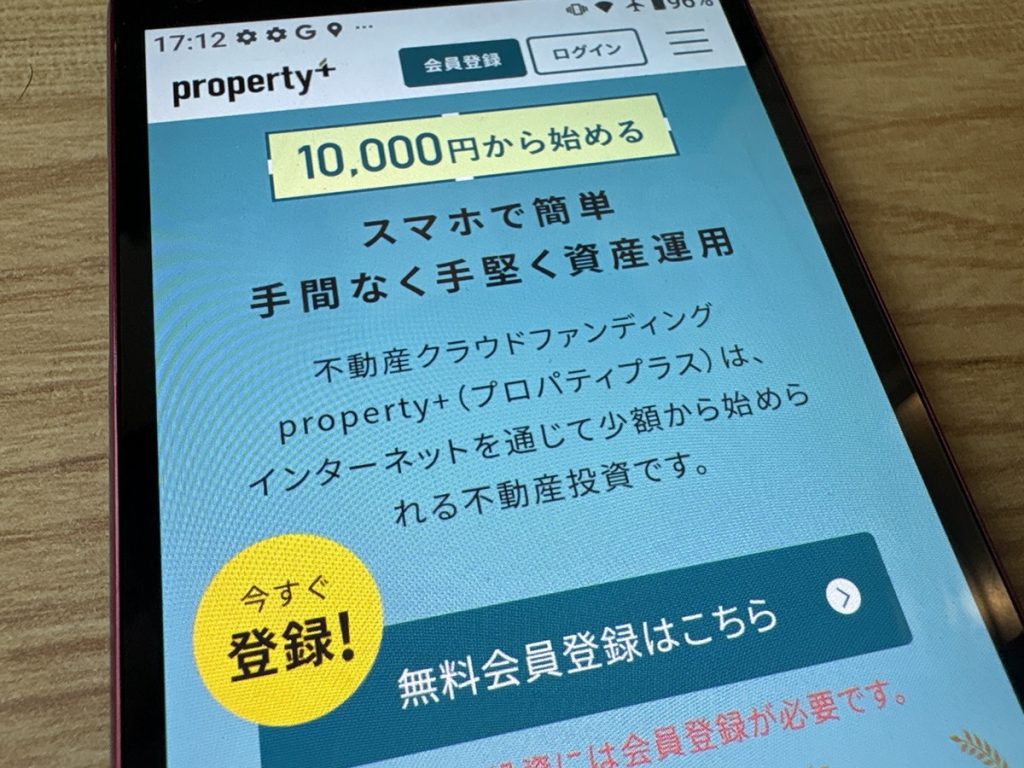
| 運営会社 | 株式会社リビングコーポレーション |
|---|---|
| 劣後出資比率 | 平均20%(4〜70%まで幅広い) |
| 最低投資金額 | 1万円 |
| 累計募集実績数 | 33件(自社商品:15件/他社商品:18件) |
| 元本割れ・分配遅延 | 0件 |
| 平均利回り | 3.0〜10% |
property+は、東証プライム上場企業「飯田グループホールディングス」のグループ会社である「株式会社リビングコーポレーション」が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
東京や名古屋、福岡などの都市圏でマンションやアパート開発を手がけており、幅広く事業展開しています。
property+の大きな特徴は、「自社商品」と「委託商品」の2種類の投資案件を提供している点です。
それぞれの違いは以下の通りです。
| 項目 | 自社商品 | 委託商品 |
|---|---|---|
| 投資対象 | 運営会社が自ら開発・運用する自社物件 | 他社が開発・運用する物件 |
| 運用管理 | 募集・運用ともに運営会社が直接担当 | 募集のみ運営会社が担当、本運用は他社 |
| 運用期間 | 3ヶ月程度の短期が多い | 1年前後の長期が多い |
| 出資金の入金方法 | 出資契約成立後に入金 | 事前に入金が必要 |
| 劣後出資比率 | 20〜70%と高め | 約4%と低め |
| 利回り | 3.0〜10%と幅広く高め | 3.2〜3.5%と安定型 |
特に、自社商品のファンドでは劣後出資比率が高く設定されているのがポイントです。
例えば、過去に組成された「Brance阿佐ヶ谷ファンド7」では、劣後出資比率が70%と非常に高い水準を記録しており、投資家の元本保全性を重視した設計となっていました。
投資スタイルやリスク許容度に応じて、柔軟で分散的な資産運用ができる点が、property+の大きな魅力です。
えんfundingの劣後出資比率は平均20%
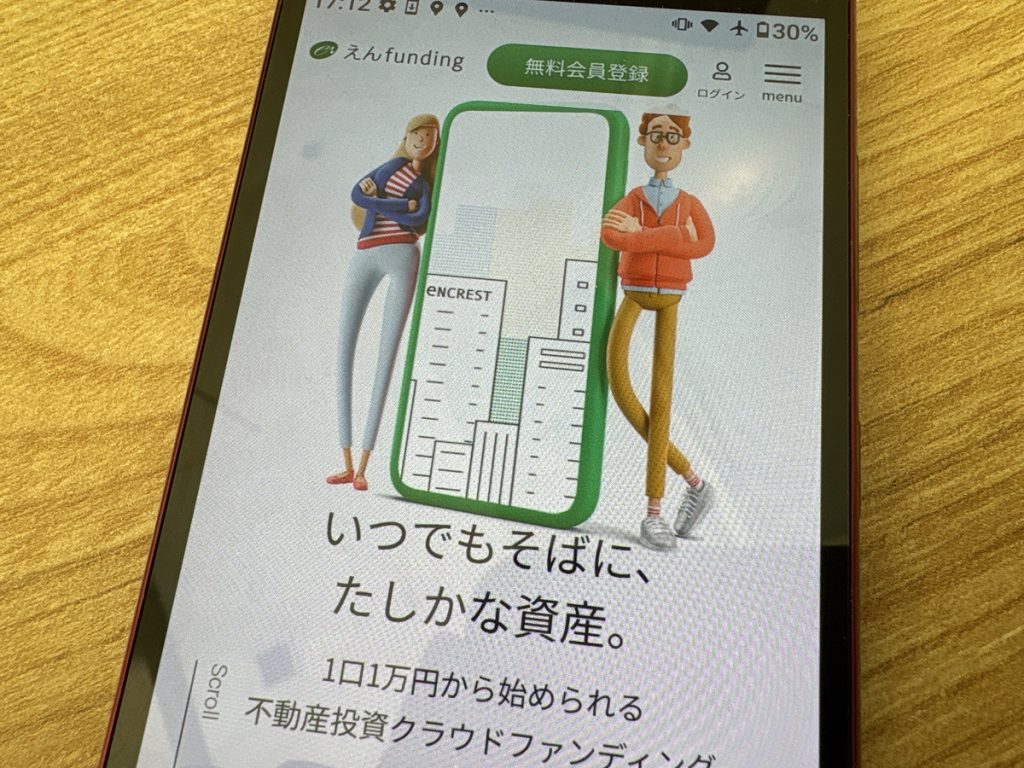
| 運営会社 | 株式会社えんホールディングス |
|---|---|
| 劣後出資比率 | 平均20% |
| 最低投資金額 | 1万円 |
| 累計募集実績数 | 43件 |
| 元本割れ・分配遅延 | 0件 |
| 平均利回り | 4〜6%が中心 |
えんfundingは、創業30年以上の実績を持つ総合不動産デベロッパー「えんホールディングスグループ」が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
福岡市を中心に不動産開発や管理を手がけてきた専門家が、地元事情に精通した情報網を活かして、希少性の高いデザイナーズマンションなど厳選した物件を提供しています。
劣後出資比率は平均20%と業界内でも高めに設定されており、万が一の損失時にも運営側が先に負担することで、投資家の元本割れリスクを抑える構造になっています。
老舗企業ならではの安定した経営基盤と信頼性も安心材料の一つで、地域を分散して投資したい方にもおすすめのサービスです。
劣後出資とは?優先劣後構造の仕組みをわかりやすく解説
劣後出資とは、不動産クラウドファンディングにおいて事業者(運営会社)が自己資金として投じる出資分のことを指します。
「劣後」には「順番が後になる」という意味があり、その名の通り投資家の出資(優先出資)よりも後に分配や返済を受ける仕組みです。
つまり、万が一の損失が発生した場合には、まず劣後出資分から損失が補填されるため、投資家の元本が優先的に保護される構造になっています。
ここでは、不動産クラウドファンディングにおける劣後出資と優先出資の関係や計算例、一般的な劣後出資比率の目安などを詳しく解説するので、参考にしてみて下さい。
不動産クラファンにおける劣後出資・優先出資の計算例
不動産クラウドファンディングにおける劣後出資と優先出資の計算例を解説します。ここで、総額1億円のファンドの劣後出資と優先出資の割合を、以下の数値と想定して考えてみましょう。
| 出資区分 | 出資額 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 劣後出資(事業者) | 2,000万円 | 20% |
| 優先出資(投資家) | 8,000万円 | 80% |
| 合計 | 1億円 | 100% |
この場合、ファンド運用中に不動産の評価額が下がったり損失が出たりした際には、まず事業者の「劣後出資」から損失が充当されます。事業者の出資部分でカバーしきれない損失が20%以上発生したときに初めて、「優先出資」である投資家の出資元本に影響が及ぶという仕組みです。
つまり、劣後出資比率が高いほど、損失が事業者側で吸収される余地が大きくなり、投資家にとって元本の安全性が高まります。このような仕組みから、劣後出資比率が高いファンドを選ぶとリスクが抑えやすいということが分かります。
不動産クラウドファンディングにおける劣後出資比率の平均は10.2%
不動産クラウドファンディングにおける劣後出資比率は、投資家にとって重要なリスク判断材料の一つです。不動産クラウドファンディング協会に加盟する事業者が提供するファンドの劣後出資比率の平均は約10.17%で、おおむね5%〜20%の範囲に収まることが多いです。
ただ、実際にはサービスやファンドごとに設定は大きく異なり、5%未満の低水準もあれば、反対に50%を超える高水準を誇る案件まで幅広く存在します。
劣後出資比率は、比率が高いほど損失発生した際に事業者側で吸収できる範囲が広くなるため、投資家の元本が守られやすくなる特徴があります。
なお、劣後出資比率は、各サービスの公式サイト内で利回りのように目立って表示されていない場合も多いです。実際にサービスに登録し、個別案件の詳細を確認しないと把握できないケースも少なくありません。リスクを抑えた投資判断をするためにも、事前に劣後出資比率をしっかり確認しましょう。
劣後出資比率が高い不動産クラファンのメリット
劣後出資比率が高い不動産クラウドファンディングのメリットは、以下の通りです。
1つずつ解説しますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
元本割れのリスクが大幅に減る
劣後出資比率が高い不動産クラウドファンディングサービスの最大のメリットは、投資家の元本割れリスクが大幅に軽減される点にあります。劣後出資とは、運営事業者が自己資金を出資する部分のことで、まず劣後出資分から優先的に損失が補填される仕組みです。そのため、劣後出資比率が高いほど、投資家の資金が損失の影響を受けにくくなり、安全性が高まります。
元々「優先劣後出資構造」は投資家保護を目的として導入された制度であり、運営会社側がより多くのリスクを背負う仕組みです。そのため、運営会社には慎重な案件選定や管理が求められ、結果的にファンド全体の健全性や安定性にも繋がっています。
劣後出資比率の高さは、サービスそのもののリスク管理意識や信頼性の高さを示す指標と言えるため、ファンドを選ぶ際の大きな判断材料となるでしょう。
安定した収益(配当)を得やすい
劣後出資比率が高い不動産クラウドファンディングサービスのメリットとして、安定した収益が得やすい点も挙げられます。例えば、不動産の運用成績が予想を下回り利益が減少した場合でも、まず事業者が自己出資した劣後部分の利益が優先的に削られるのが、優先劣後構造の仕組みです。
これにより、投資家の優先出資分は先に保護されるため、投資家への配当は計画通り支払われる可能性が高くなります。実際、劣後出資比率が高いファンドでは、事業者がリスクを背負う構造となっており、その分だけ投資家の収益の安定性が確保されやすくなります。
劣後出資比率の高さは、投資元本だけでなく配当面でも投資家にとって安心材料となる大きなメリットと言えるでしょう。
事業者と投資家の利害が一致する
事業者が自己資金を劣後出資として投じることで、「運用がうまくいかなければ自分も損をする」という明確なリスク共有の構造が生まれます。そのため、事業者と投資家の利害関係が一致し、事業者は自己資金を守るためにも慎重かつ責任感を持って資産運用に取り組む強い動機付けが発生します。
結果として、事業者の運用姿勢がより真剣かつ透明性の高いものとなり、投資家は安心して投資できる環境が整う流れに繋がるでしょう。劣後出資は単にリスク分散にとどまらず、事業者の責任感と信頼性を高める役割も果たしており、不動産クラウドファンディングの健全な運営に不可欠な仕組みであると分かります。
劣後出資比率が高い不動産クラファンのデメリット
劣後出資比率が高い不動産クラウドファンディングは投資家の元本保全に有効ですが、元本割れのリスクが完全に消えるわけではありません。また、運営事業者の倒産や重大な経営トラブルなどのリスクも存在しています。
これらのリスクを理解し、適切に対処することが重要です。ここで、劣後出資比率の高さにあるデメリットと注意点を解説するので、ぜひ参考にしてみて下さい。
元本割れの可能性がゼロになるわけではない
劣後出資比率が高い不動産クラウドファンディングは、投資家の元本割れリスクを大幅に軽減しますが、元本割れの可能性がゼロになるわけではありません。想定を超える大規模な価格下落や予期せぬトラブルが発生した場合、劣後出資分を超える損失が生じることもあり得ます。
例えば、不動産市況の急激な悪化や大規模な災害、運営側の重大な過失などが起こると、事業者の出資分だけでは損失をカバーしきれず、投資家の元本に影響が及ぶリスクは残ります。つまり、劣後出資比率が高くてもリスクを完全に排除するものではないため、投資判断においては慎重な検討が必要な点を把握しておきましょう。
事業者倒産など防げないリスクもある
劣後出資比率が高くても、事業者の倒産などのリスクは完全には防げません。劣後出資比率が高く設定されていても、運営会社が倒産すればファンドの適切な管理や資産売却が困難になり、投資家の元本回収や分配金の支払いに支障をきたす可能性があります。
さらに、倒産に伴う資産流動化の遅延や法的手続きの複雑化により、投資家への返還が長期化・減少するリスクも存在します。そのため、劣後出資比率の高さだけに頼らず、運営会社の信用力や経営の健全性を見極めることも重要なポイントです。
不動産クラウドファンディングにおいては、運営会社がファンドの管理や運用を担うため、事業者の財務状況や経営体制が非常に重要です。事前に運営会社の実績や財務状況を確認しておくことで、より安心して不動産クラウドファンディングを始められるでしょう。