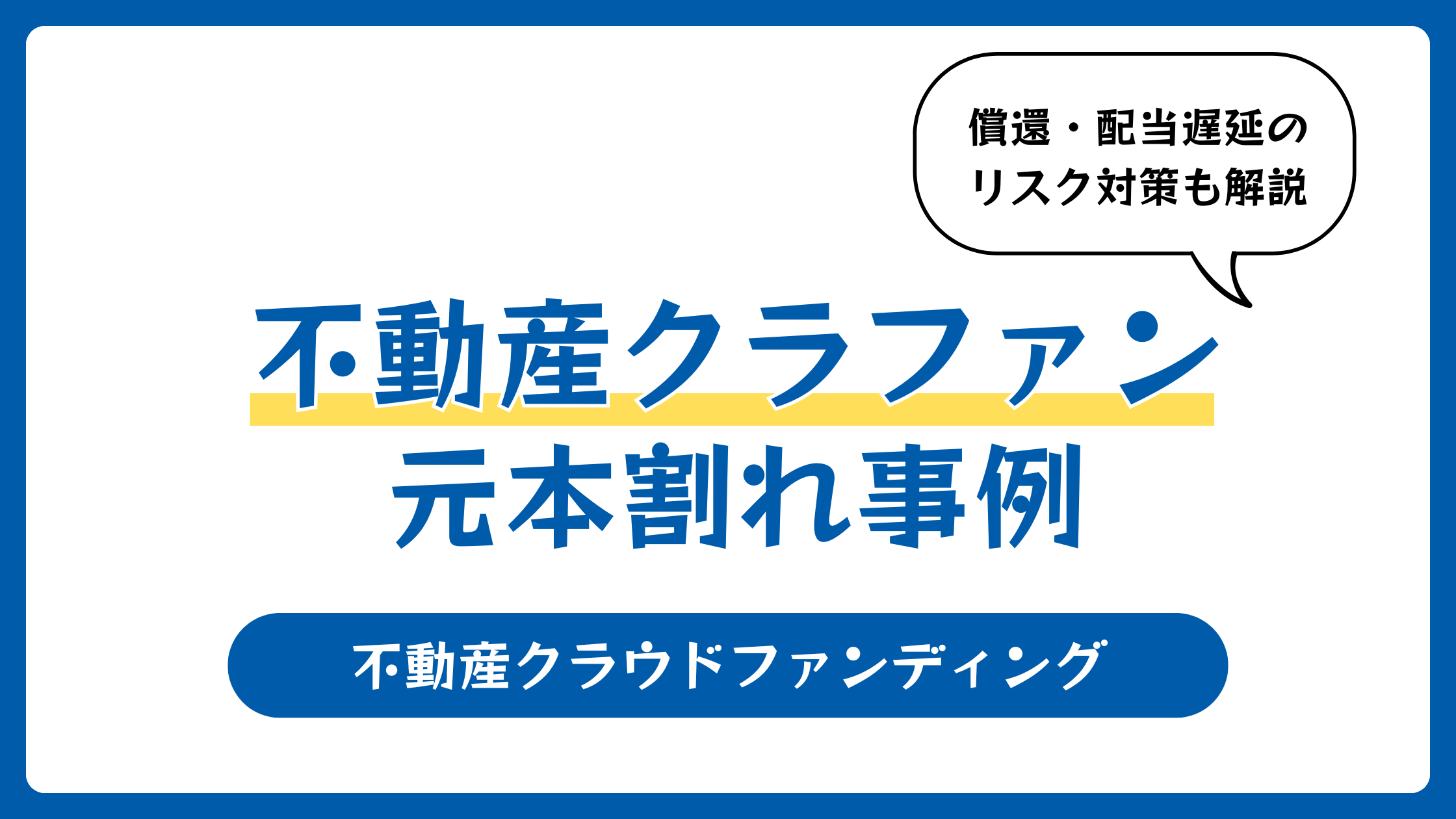不動産クラウドファンディングは、少額から始められ高利回りを期待できる不動産投資の手法です。
一方で、2025年9月時点で、償還遅延や分配金の遅配、さらには運営会社の破産申告など、投資家を不安にさせるトラブルも確認されています。
「元本割れ」が確定した事例はまだないものの、ニュース番組やSNS上でもリスクを懸念する声は増加傾向にあります。
高い利回りという魅力に隠れたリスクを理解し、慎重に投資を行うことが大切です。
本記事では、実際に起きた償還遅延や配当遅延の事例を整理し、安全に不動産クラウドファンディングを活用するためのポイントを解説します。
ぜひ参考にしてみて下さい。
不動産クラウドファンディングの元本割れが起こった事例はない
現在、不動産クラウドファンディングにおいて元本割れの事例は確認されていません。
ただ、法律上「元本保証」は禁止されているため、各事業者が示す「元本割れの実績ゼロ」という表現は安心材料を示しているものの、あくまでも参考情報です。
実際に、2025年7月に「DAIMLAR FUND」の運営会社が破産したほか「ヤマワケエステート」や「みんなで大家さん」でも遅延が発生しています。
「元本割れ事例は存在しない」とする表現は必ずしも安全性を担保するものではありません。
過去の実績や運営会社の経営状態を事前に把握し、リスクをしっかり認識したうえで投資判断をすることが大切です。
元本割れ未確定だがリスクのある不動産クラファンの事例
不動産クラウドファンディングでは、過去の運用実績を根拠に「元本割れは発生していない」と説明されることが多く、投資家にとって安心材料となる場合があります。
一方で、法律上は元本保証が認められておらず、会社全体の破産や運用上のトラブルにより出資金が戻らないリスクは存在します。
ここでは、元本割れは未確定ながらも、実際にリスクが現れた事例として「DAIMLAR FUND」の状況をご紹介します。
DAIMLAR FUND(ダイムラーファンド)

「DAIMLAR FUND」は、1万円から投資できる不動産クラウドファンディングを提供していました。
ところが、2025年7月に運営会社の「ダイムラー・コーポレーション」が横浜地方裁判所から破産手続き開始決定を受け、サービスが停止しています。
概要は以下の通りです。
| 運営会社 | 株式会社ダイムラー・コーポレーション |
|---|---|
| 設立 | 2007年 |
| 破産手続開始決定 | 2025年7月(横浜地方裁判所) |
| 負債総額 | 約3.3億円 |
| 債権者数 | 約300人 |
| 破産原因 | ・代表者の死去(2025年6月) ・経営不振 |
2025年9月時点で投資家の出資金が戻らない可能性が高く、事実上の元本割れに該当する可能性が指摘されています。
匿名組合型ファンドの仕組み上、投資家は物件を直接所有せず、資金は破産管財人の管理下で他の債権者と同様に扱われます。
不動産クラウドファンディングの破綻は通常「案件単位」で発生しますが、本件のように運営会社そのものが破産するのは極めて稀なケースです。
今後の制度設計や事業者の健全性を見直す重要な事例と言えるでしょう。
なお、2025年9月時点で「DAIMLAR FUND」の公式サイトは閉鎖されておらず、破産手続きや債権者への情報提供を目的に存続していると思われます。
海外不動産向けのクラウドファンディングの場合、為替で損をすることがある
海外不動産クラウドファンディングでは、投資先の国の通貨が円に対して変動することで、収益や元本を円換算した際に目減りする可能性があります。
このような為替変動は、避けられない投資リスクのひとつです。
不動産クラファン系で初の元本割れを経験⚡️
【「円投資」オーストラリア不動産ローンファンド第162号】に30万円投資。償還を迎えたものの出資払戻の際に為替差で12,170円のマイナスに🫨
モッピー🐿️で10,000円、分配金で5,000円の収益があったので結果黒字ではあるけど…為替💱リスクしっかり見ます💦
X
例えば、上記の口コミでは為替変動の影響で払い戻し時に12,170円のマイナスとなり、元本割れを経験したと発信しています。
ただし、これは不動産ローン自体の損失ではなく、円換算時に生じた為替差による目減りです。
分配金やポイント収益を含めると最終的には黒字となっており、厳密な意味での元本割れではありません。
ただ、この事例は為替リスクが投資成果へ影響を与えることを示しています。為替リスクを軽減する方法としては以下のポイントをおさえることが大切です。
- 為替ヘッジ付きファンドを利用する
- 円建て対応ファンドを選ぶ
- 複数通貨に分散投資する
- 投資時期を分散してドルコスト平均法を利用する
海外不動産クラウドファンディングは高いリターンを期待できますが、為替変動により円換算での収益や元本が減少する可能性があります。運用が順調でも円高でマイナスが発生することがあるため、円建てファンドの活用や分散投資などの工夫が欠かせません。
償還遅延や分配金の配当遅延が起こり炎上した不動産クラウドファンディング事例
ここからは、2025年に償還や分配金の遅延が発生し、投資家の間で大きな問題となった「ヤマワケエステート」と「みんなで大家さん」の事例を解説します。
いずれも契約の破談や運営会社の経営不安定が背景にあり、出資金の返還や利益配当に遅れが生じました。これらの事例を通じて、不動産クラウドファンディング特有のリスクや、情報開示の重要性について整理していきましょう。
ヤマワケエステート

ヤマワケエステートは、本田圭佑氏を公式アンバサダーに起用することでも注目を集めていましたが、2025年9月時点で一部ファンドの償還遅延が発生しています。概要は以下の通りです。
| 運営会社 | ヤマワケエステート株式会社 |
|---|---|
| 親会社 | WeCapital株式会社 |
| 最終親会社 | 株式会社REVOLUTION |
| 対象ファンド | 札幌市宮の森隈研吾&Knight Frankシリーズ2nd〜4th(62号・106号・119号) |
| 償還予定日(変更前) | 2025年3月7日 |
| 償還予定日(変更後) | 2025年8月29日 |
| 遅延理由 | 対象物件の売却契約が直前で破談 |
| 炎上の背景 | ・償還予定日の前日に急遽延期が通知 ・SNSで掲示板や投資家の不安や批判拡散 ・親会社の社長交代や株主優待廃止など経営不安 |
| 構造的問題 | ・物件売却が遅れれば償還も遅延 ・リスク説明は事前に明記されていたが、急な通知や情報開示の質が問題視 |
運用終了後の償還延期に関するご説明にて半年後の2025年8月29日を新たな償還日と予定していましたが、遅延は続いており今後も延期の可能性が残されています。さらに、2025年8月には「WeCapital」が元代表取締役の松田氏に対し、償還延期や交際費未返還に関する約2億円の損害賠償請求訴訟を提起しています。
この事例は、物件売却や運営会社の経営状況が投資家の出資金償還に直結するリスクと、運営体制やガバナンス問題に対する社会的注目を示す重要なケースです。今後の状況も冷静に見極めていきましょう。
利回りジャンキー向けの不動産クラファンなら
トーチーズの公式サイトをみる15%超の案件が多数
みんなで大家さん
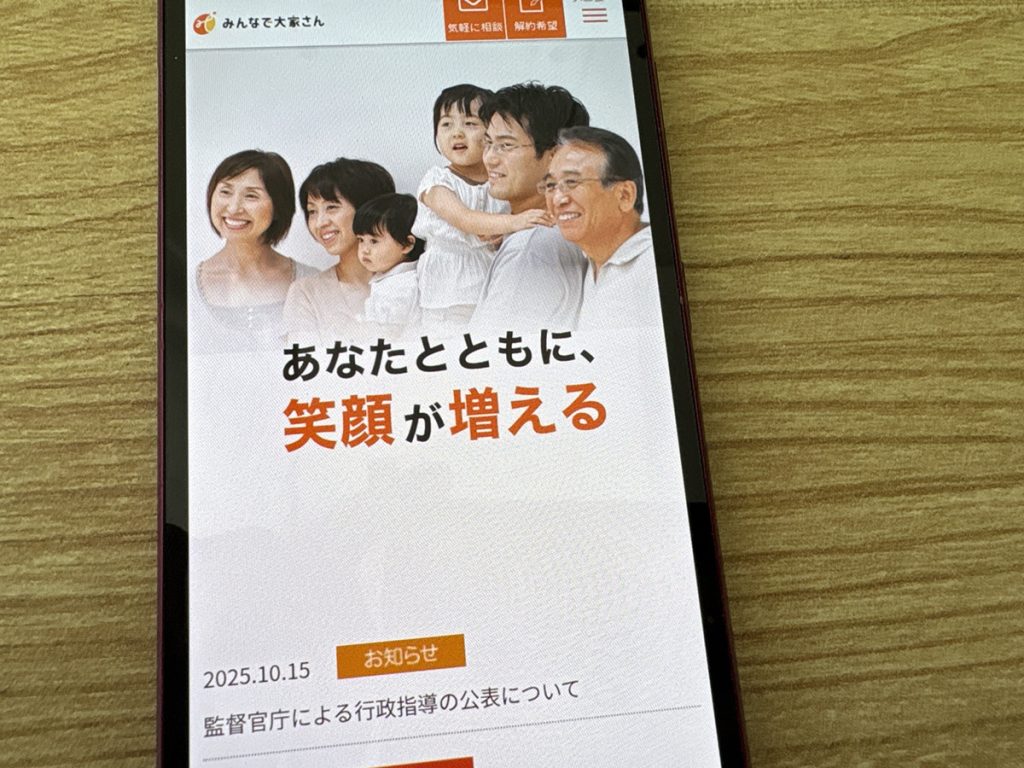
「みんなで大家さん」は、大阪を拠点とする不動産クラウドファンディングサービスで、1口100万円からの投資条件と7%前後の利回りで注目を集めていました。一方、2025年7月末に償還予定だった「成田空港周辺プロジェクト」で遅延が発生しています。概要は以下の通りです。
| 運営会社 | ・みんなで大家さん販売株式会社 ・都市綜研インベストファンド株式会社 |
|---|---|
| 対象ファンド | シリーズ成田「成田空港周辺開発プロジェクト用地」 |
| 償還予定日 | 2025年7月31日 |
| 遅延理由 | ・テナント賃料未払い ・行政処分による資金調達の困難 ・開発事業の遅延 |
| 炎上の背景 | ・分配金支払いの停止 ・投資家からの不安や批判の拡散 |
| 構造的問題 | ・大口投資1口100万円のリスクが高い ・行政からもプロジェクト実現性に懸念 |
上記の通り、開発事業の遅れにより、2025年7月から分配金の支払いが停止しています。主要物件「GATEWAY NARITA」の賃料収入遅れや解約申請の急増で、7月末及び8月末の分配も滞っています。さらに、2024年には東京都と大阪府から行政処分も受けており、行政監督下でプロジェクトの実現性について繰り返し懸念が示されていました。
また、構造上の問題として1口100万円という大口投資はリスクが高く、1万円など少額から投資できる不動産クラウドファンディングサービスの重要性も示された事例と言えます。
不動産クラウドファンディングの元本割れに関する口コミや評判
不動産クラウドファンディングの元本割れに関する口コミや評判をご紹介します。
不動産クラファンって、どこも怪しいだの危ないだのやめとけだの言われてるけど
X
経営破綻して元本割れした事例って今のところないらしいね
これからどうなるかは見ものだけど
不動産クラウドファンディングのリツイートきたけど、年利4から7%がいいところだと思う。10は危ない
あとは実績かあるところがいい。最近だと投資家のブログで口コミがすぐに広がるから不動産側も元本割れをすることを恐れてるから
調べられるなら投資してもいいと思う
X
【不動産クラファンで見落とされがちなリスク】
1万円から投資できる不動産クラファン。利回り5〜7%など魅力的な数字が並びますが、当然リスクも存在します。
📌 元本保証はなく、最悪ゼロになる可能性も
📌 途中解約ができないため資金拘束リスクがある
📌 運営会社の経営破綻や不正が起きれば回収困難こうした特性は、株や投信とは異なる“流動性の低さ”に直結します。
だからこそ「余裕資金で取り組む」「信頼できる運営会社を選ぶ」ことが必須。資産運用では「リターンの裏にあるリスク」を理解して初めてバランスが取れます。
結局のところ、資産形成は【安心と成長の両立】をどう設計するか。その考え方については固定ポストで詳しくまとめていますので、ぜひご覧ください。
X
不動産クラウドファンディングは少額から高利回りが狙える投資として人気ですが、元本保証がない点に注意が必要です。また、途中解約できず資金が拘束されることや、運営会社の経営破綻や不正による回収困難リスクも指摘されています。
口コミでは、利回りだけに目を向けると危険との声があり、余剰資金と信頼できる運営会社を選ぶことの大切さが分かります。
不動産クラウドファンディングでは元本保証は禁止されている
不動産クラウドファンディングでは、元本保証は法律で厳格に禁止されています。主に「出資法」と「不動産特定共同事業法第21条の2(金融商品取引法第42条に準ずる規定)」に基づき、国土交通省や金融庁に規制されています。
なお、元本保証できない代わりに多くの案件では優先劣後構造を採用し、投資家の損失を一定範囲で軽減しています。ただ、あくまでもリスクの分散の仕組みであり、元本が完全に保証されるわけではありません。
償還や分配の遅延、事業者の経営不振や不動産価格の下落などにより、元本割れが発生する可能性は存在します。不動産クラウドファンディングをする際は、法的背景やリスクを理解したうえで、余剰資金で運用することが大切です。
具体的な規制や監督方針については、以下の国土交通省の公式ページもご参照下さい。
不動産クラウドファンディングで元本割れや償還遅延が少ない理由
金融庁の公式資料「不動産特定共同事業者の監督をめぐる動き」によると、法的許可を受けている不動産特定共同事業者は、2024年6月30日時点で256社存在します。
先にご紹介した遅延報告やリスクのある3業者は、全体に対する約1.17%にとどまり、業界全体で見ると元本割れや償還遅延は比較的少ないと言えるでしょう。その背景には、法律による規制やスキーム構造、運営会社のリスク管理が大きく関わっています。
ここで、不動産クラウドファンディングで元本割れや償還遅延が少ない理由を整理すると、主に以下の4点が挙げられます。
それぞれ詳しく解説するので、参考にしてみて下さい。
事業者の規制・許認可・分別管理
不動産クラウドファンディング事業者は、不動産特定共同事業法など関連法制度の下で運営されています。これらの法令は、事業者に情報開示義務や運営社の資産・責任の明確化を求めることで、透明性の高い運営を義務付けています。
また、出資金の分別管理を求められる可能性が高く、事業者が倒産した場合でも投資家資金への影響を限定できる構造が特徴です。こうした法的枠組みと運営体制により、業界全体で元本割れや償還遅延のリスクは比較的低く抑えられています。
規制や許認可に関する詳細は、国土交通省の不動産特定共同事業についての資料もご参照下さい。
優先劣後スキームの存在
多くの不動産クラウドファンディングでは、投資家保護の仕組みとして「優先劣後方式」が導入されています。運営事業者が自己資金を「劣後出資」として一定割合負担するため、運用中の損失は、まずは事業者の出資分から吸収される仕組みです。
そのため、不動産価格の下落や収益が悪化した場合でも、投資家の元本がすぐに毀損する可能性は低くなります。劣後出資割合が大きいほど、元本保護の余地が広がり、元本割れのリスクはさらに抑えられます。
「優先劣後方式」の存在が、業界全体で元本割れや償還遅延の発生が比較的少ない理由のひとつです。ただ、劣後出資の比率はサービスごとに異なるため、ファンド選びの際には必ず事前に確認することが安全性を見極めるポイントです。
サービスが一般化してから歴史が浅いこと
不動産クラウドファンディングは比較的新しい投資手法で、市場自体が成長途上です。そのため、データが不十分なことから元本割れや遅延の前例はまだ少ない状況です。
業界が浸透した背景には、2017年12月1日の不動産特定共同事業法の法改正が大きく関わっています。この改正で「小規模不動産特定共同事業」が設けられ、資本金や出資総額の要件が大幅に緩和されました。地方創生の観点でも注目され、国土交通省の不動産特定共同事業に関する制度のあり方に関する報告書でも制度のあり方が取り上げられました。
このようにサービス自体の歴史が浅いため、現時点で元本割れや償還遅延の事例は限られています。ただ、データが充分に蓄積されていないため、今後の市場拡大に伴い新たなリスク事例が出てくる可能性はあります。投資判断の際にはリスクを理解したうえで、余剰資金で運用することが大切です。
運営する不動産会社による慎重な案件選定
不動産クラウドファンディングでは、運営会社による慎重な案件選定が重要です。事業者は法律に基づき、投資家から預かった資金で不動産の売買や賃貸を行うため、適切な物件選びや運営管理が不可欠です。特に小口化案件では、事業者の経営破綻が元本毀損リスクに直結するため、財務基盤や実績、蓄積されたノウハウが安定性を大きく左右します。
さらに、事業者には許可制や登録制により、資本金や人的資源の確保、情報開示義務などが法律で担保されており、健全な運営が求められます。
結果として、多くのファンドでは都心や交通アクセスが良く、需要が見込める物件を中心に選定し、リスクの高い案件を避ける設計をするのが特徴です。こうした慎重な案件選定と法的枠組みにより、元本割れや遅延の事例が比較的少ないと言えるでしょう。
元本割れや償還遅延といった失敗やトラブルを避ける方法
ここで、不動産クラウドファンディングで元本割れや償還遅延といった失敗やトラブルを避けるための方法を5つ解説します。
それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。
劣後出資比率が20%以上の案件を選ぶ
多くの不動産クラウドファンディングでは、投資家保護の仕組みとして「優先劣後方式」が採用されています。劣後出資比率が大きいほど投資家の資金が保護される余地が広がるため、劣後比率が高いクラファン案件を選ぶことがおすすめです。
劣後出資比率はサービスにより異なり、10%以下の低い比率から30%以上の高い比率まで幅があります。目安としては20%以上の案件を選ぶと、リスクが抑えやすくなります。参考までに、総額5,000万円のファンドを想定してみましょう。
| 出資区分 | 出資額 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 劣後出資(事業者) | 1,000万円 | 20% |
| 優先出資(投資家) | 4,000万円 | 80% |
| 合計 | 5,000万円 | 100% |
上記のケースでは、損失が20%以内であれば事業者の劣後出資でカバーされ、投資家の資金には影響がありません。案件を選ぶ際には、劣後出資比率を確認することが安全性を見極めるポイントのひとつです。
1年以内の短期運用ができる案件を選ぶ
不動産クラウドファンディングで投資リスクを抑えるためには、運用期間が短いクラファン案件を選ぶことがおすすめです。特に1年以内の短期案件は資金回収までの期間が明確で、市場の価格変動や運営上の不確実性の影響を受けにくくなります。
長期案件と比べて、経済環境の急変や不動産価値の下落など不測の事態の影響が少なく、元本割れや償還遅延のリスクを相対的に軽減できます。また、資金回収のタイミングが早いことで次の投資や資金運用の計画も立てやすく、安心感が高まるのも魅力です。
このように、短期案件はリスク管理で安定した運用を重視する投資家に最適な選択肢です。
過去の償還実績が多い不動産クラファンを選ぶ
不動産クラウドファンディングでは、過去に多くの案件を予定通り償還してきたサービスを選ぶことが、投資の安心につながります。多数の案件を運用し、予定通りに元本と分配金を償還してきた実績は、運営体制の安定性やリスク管理能力の高さを示します。実績のある事業者は、物件選定や資金運用のノウハウが蓄積されており、突発的なトラブルにも柔軟に対応できる可能性が高いです。
また、透明性の高い情報開示や投資家への丁寧な報告を継続していることも、信頼性の重要な指標です。
一方で、実績の少ない事業者はリスクの判断材料が乏しく、投資家として不安が残ります。
そのため、過去の償還実績を確認することは、投資判断の大切な基準のひとつと言えるでしょう。
上場企業が運営する不動産クラファンを選ぶ
不動産クラウドファンディングサービスを選ぶ際に注目したいポイントのひとつが、運営会社が上場企業かどうかです。上場企業は金融商品取引所の厳しい基準をクリアしており、定期的な監査や詳細な情報開示が義務付けられています。そのため、財務状況や経営体制の透明性が高く、安定した運営が期待できる点が魅力です。
不動産クラウドファンディングは投資家の資金で不動産を運用するため、運営会社の基盤が不安定だと元本や償還のリスクが高まります。上場企業であれば、法律や取引所の基準で管理体制が担保され、リスク管理も比較的信頼できます。また、上場企業は社会的信用を重視するため、不透明な運営や不正リスクにも非常に慎重です。
未上場企業でも安定したサービスは存在しますが、安全性を重視する投資家にとっては「上場企業が運営しているかどうか」を判断基準に加えることをおすすめします。
複数の不動産クラファンに分散投資をする
不動産クラウドファンディングでの分散投資は、元本割れや遅延などのトラブルを避けるための有効な手法です。1つの案件に資金を集中させるのではなく、複数の案件や異なる運営会社に分散することで、投資リスクを軽減できます。
複数の運営会社に分散投資すれば、より安定した収益の実現につながります。このように分散投資は、投資家自身がコントロールできる、有効なリスク管理手段のひとつです。
なお、以下の記事ではおすすめの不動産クラウドファンディングサービス12選の特徴を比較してご紹介しています。ぜひ参考にしてみて下さい。