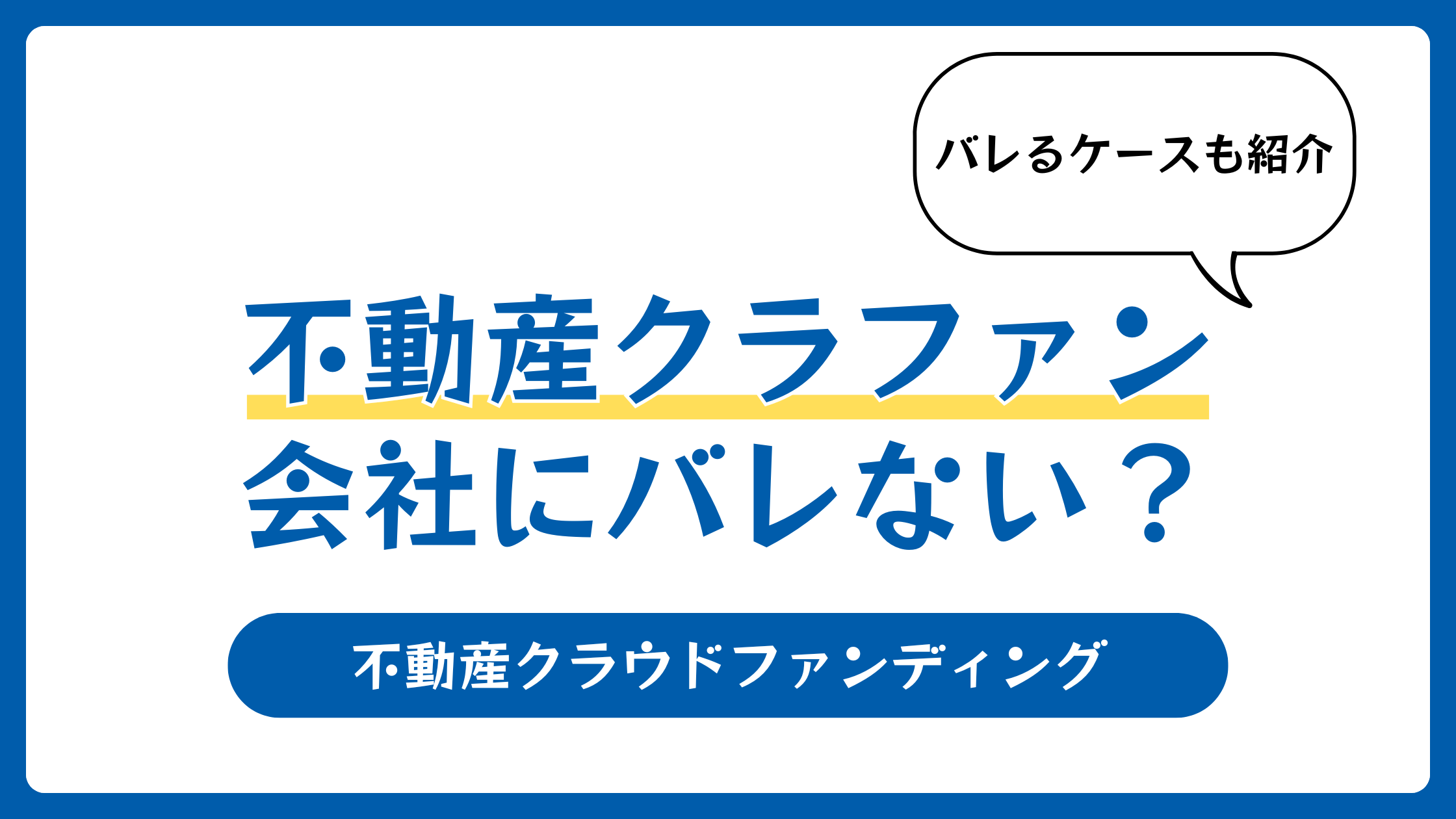不動産クラウドファンディングに興味はあるけれど、「もし会社にバレて評価や昇進に影響したら」と不安に感じる方は少なくありません。
実際には、会社に伝わってしまうケースはごく限られており、基本的には問題なく利用できます。
ただ、それでも事前に仕組みや注意点を知っておくことで、安心して投資を始められるでしょう。
そこで本記事では、会社にバレる可能性があるケースや、確定申告が必要となる条件などを解説します。
不動産クラウドファンディングを始めてみたいけど、会社にバレないか気になっている方はぜひ参考にしてみてください。
【結論】不動産クラウドファンディングへの投資がバレないか心配する必要はない
不動産クラウドファンディングに興味を持ちながらも、「会社に知られてしまうのでは」と不安を感じる方は少なくありません。
特に副業禁止規定を気にする人にとっては大きな懸念点でしょう。
しかし結論から言えば、投資が会社に伝わる可能性は極めて低く、心配する必要はありません。
さらに仮に知られたとしても、不動産クラウドファンディングは副業ではなく資産運用にあたるため、規則違反に該当することもありません。
そもそもバレても問題はない
不動産クラウドファンディングへの投資は、企業に勤めている人が副業として行う「労働」ではなく、あくまで金融商品の運用にあたります。
そのため会社の就業規則で禁止される副業には該当せず、仮に会社に知られたとしても規則違反にはなりません。
実際、多くの人が株式や投資信託と同じ感覚で資産運用として利用しており、特別に報告する義務も課されていないため、心配する必要はないのです。
バレることはあまり無い
不動産クラウドファンディングへの投資は、基本的に会社に伝わる仕組みがありません。
証券口座やクラウドファンディング口座の利用は個人の資産運用にあたり、勤務先へ情報が共有されることはないからです。
税金の処理も源泉徴収ありの案件を選べば確定申告の必要がなく、会社に知られる機会はほとんどありません。
詳しくは後述しますが、通常の運用であれば「会社にバレる心配はほぼ無い」と考えて問題ないでしょう。
不動産クラウドファンディングは副業扱いにならない
不動産クラウドファンディングは基本的に副業にはあたりません。
得られる利益は投資による収益とみなされるため、会社員や公務員でも安心して取り組めるケースが多いのです。
ただし、企業によっては就業規則の中で副業や兼業を広く定義している場合もあるため、念のため確認しておくと安心です。
ここでは、不動産クラウドファンディングが副業扱いされない理由や、会社規程をチェックすべきポイント、さらに契約形態による違いについて解説します。
基本的には副業ではなく投資扱い
不動産クラウドファンディングは、企業での労働によって収入を得る「副業」とは異なり、株式投資や投資信託と同様に「資産運用」として扱われます。
自分の資金を運用して配当や利益を得る仕組みのため、会社の就業規則で禁止されるような副業には該当しません。
そのため、副業を原則禁止している会社員や公務員でも安心して利用できるケースが一般的です。
法律的にも制度上も投資として整理されているので、副業違反になる心配はありません。
気になる方は会社の就業規則を確認
不動産クラウドファンディングは副業ではなく資産運用にあたるため、基本的には会社員や公務員でも問題なく行えます。
ただし「副業」や「兼業」の定義は会社によって微妙に異なる場合があります。
まれに投資による収益についても制限を設けている企業があるため、不安な方は就業規則を確認しておくと安心です。基本的には投資禁止を明記しているケースは少なく、ほとんどの場合は心配せずに利用できるでしょう。
不動産クラファンの種類に注意
不動産クラウドファンディングは「不動産特定共同事業法」の枠組みで提供され、契約形態によって税務上の扱いが異なります。代表的なのは「匿名組合型」と「任意組合型」です。
匿名組合型(契約型CF)は、投資家は不動産を直接所有せず、事業者に出資して配当を受け取る仕組みです。得られる利益は雑所得扱いとなり、給与や事業所得とは別枠で処理されます。そのため、一般的には「副業」とは見なされにくい性質を持ちます。
一方、任意組合型(現物出資型CF)は、投資家が不動産の持分を共有する形態で、不動産投資に近い仕組みです。持分を譲渡する際には譲渡所得扱いとなる可能性があります。ただし、これも事業所得とは別枠であり、税務上「副業」とされるわけではありません。しかし、不動産投資に近い性質を持つため、勤務先によっては広義の副業と解釈される余地もあり、注意が必要です。
詳しくは、国土交通省「クラウドファンディングを活用した不動産特定共同事業に係る資料」、 国土交通省「不動産特定共同事業の利活用促進ハンドブック」をご確認ください。
不動産クラウドファンディングへの投資が会社にバレるケース
不動産クラウドファンディングは基本的に副業扱いではありませんが、会社に知られたくないと考える方も多いでしょう。実際には、税務処理や日常のちょっとした行動がきっかけで周囲に気づかれる可能性があります。
たとえば、SNSで投資状況を投稿してしまう、同僚にうっかり話してしまう、あるいは社用端末やオフィスのWiFiでサービスにアクセスすることなどが典型的です。また、会社のメールアドレスや電話番号で登録したり、書類の送付先を会社にしてしまうと情報が共有されるリスクが高まります。さらに、確定申告後に住民税が増えて不審に思われるケースもあるため注意が必要です。
ここでは、典型的なケースを以下の7つにしぼって解説します。
それぞれのケースを詳しく解説します。
SNSに書き込むケース
不動産クラウドファンディングを始めたことを、SNSでつい発信してしまうケースは少なくありません。「利回り○%に投資しました」「初めて分配金が入った!」といった何気ない投稿でも、思わぬところから会社関係者の目に触れる可能性があります。特に実名や顔写真を使っている場合、本人と結びつくリスクは高まりますし、匿名アカウントでもフォロワーの中に同僚や取引先がいることも考えられます。
また、投稿内容から個人を特定できる勤務先などが推測されることもあるため注意が必要です。SNSは公開範囲を制限できるものの、完全にコントロールすることは難しいため、会社に知られたくないのであれば投資関連の発信は控えるのが無難でしょう。
職場の同僚や先輩、後輩に口をすべらすケース
会社に知られたくないと思っていても、日常の会話の中でつい口をすべらせてしまうケースがあります。たとえば「最近投資を始めて」「分配金が入って助かった」など、軽い雑談のつもりでも相手によっては敏感に受け取られることがあります。特に先輩や上司との会話であれば「副業なのでは?」と誤解されやすく、噂が広まるきっかけになりかねません。
また、同僚同士の飲み会やランチといったリラックスした場面でも情報が漏れる可能性があります。小さな発言がきっかけで意図せず広がってしまうため、不動産クラウドファンディングをしていることは、信頼できる人に限定するか、基本的には話題にしない方が安心です。
社用のスマホやPCでアクセスするケース
社用で貸与されているスマホやPCを使って、不動産クラウドファンディングのサイトやマイページにアクセスするのはリスクが高い行動です。会社の端末にはアクセス履歴や利用状況を監視するシステムが導入されている場合があり、業務に関係のないサイトへの接続はすぐに把握される可能性があります。
また、たとえ監視がなくても、ふとしたタイミングでブラウザの履歴や通知を同僚に見られてしまうことも考えられます。さらに、端末に保存した書類やスクリーンショットが誤って共有されるリスクもあるでしょう。会社に投資活動を知られたくないのであれば、業務用端末は仕事での使用のみ、投資関連の操作は必ず自分の私用端末で行うことが基本です。
勤務時間中にオフィスのWiFiなどでログインするケース
勤務時間中に会社のWiFiやネットワークを使って、不動産クラウドファンディングのサイトにアクセスすることも注意が必要です。業務用ネットワークでは、接続先の履歴やトラフィックを監視している場合があり、業務に関係のないサイトへのアクセスは記録される可能性があります。
また、他の社員が同じネットワークを使っている場合、ブラウザの履歴や画面を偶然目にして情報が漏れることも考えられるでしょう。たとえ監視が厳しくない環境でも、勤務中のアクセス自体が副業や業務外活動と誤解されるリスクがあります。そのため、投資に関する操作や確認は勤務時間外、かつ社用ネットワークを使わずに行うのが安全です。
会社のメールアドレスや電話番号で会員登録をするケース
不動産クラウドファンディングの会員登録に、会社のメールアドレスや電話番号を使うことも情報漏えいのリスクにつながります。登録情報は運営会社からの通知や書類送付、システム上の管理情報に反映されるため、会社のメールに届いた連絡を同僚や上司が目にする可能性があります。また、電話番号を登録している場合、本人確認や連絡の際に会社に関連付けられることがあります。
さらに、メールアドレスから会社名が推測されると、投資活動が勤務先に知られるきっかけになることもあるため注意が必要です。投資活動を社内に知られたくない場合は、個人のメールアドレスや電話番号を使い、会社の連絡先は絶対に利用しないようにするのが安全です。
書類の送付先や連絡先を会社宛にするケース
不動産クラウドファンディングの契約や分配金に関する書類を、会社の住所や連絡先にしてしまうと、意図せず投資活動が会社に知られるリスクがあります。特に紙の書類が郵送される場合、同僚や総務担当者の目に触れる可能性があります。また、メールや電話での連絡先を会社の情報にしている場合も、通知が会社に届くことで気づかれることがあるかもしれません。
さらに、契約書や分配金明細が会社の端末や共用設備に保管されると、誤って他人に見られることも考えられます。投資内容を会社に知られたくない場合は、必ず自宅の住所や個人のメール・電話番号を登録し、会社宛に書類が届かないように設定することが安全です。
自身で確定申告をして、住民税額の多さから不審に思われるケース
副業が会社に知られる可能性が特に高いのは、多額の利益を得て、自身で確定申告を行った場合です。確定申告をすると、その内容が住民税に反映されるため、給与以外の所得があると住民税額が通常より多くなり、会社の経理担当者が不審に思う可能性があります。これが最も典型的なバレるケースです。
それ以外のケースについては、自分自身が情報の扱いに注意していれば、会社に伝わるリスクはほとんどありません。なお、確定申告が必要な状況については後述しますが、もし確定申告を行わない範囲で投資や副収入を得ているのであれば、住民税を通じて会社に知られる心配は基本的にありません。
源泉徴収される匿名組合型の不動産クラウドファンディングでも確定申告は必要?
不動産クラウドファンディングの多くは「匿名組合型」で提供されています。この仕組みでは、運営会社があらかじめ所得税を源泉徴収したうえで、投資家に分配金を支払うのが一般的です。そのため、受け取る段階で既に税金が差し引かれており、基本的には投資家が追加で確定申告を行う必要はありません。
ただし注意したいのは、住民税については源泉徴収の対象外となっている点です。具体的には、以下のような場合に自ら確定申告を行う必要があります。
つまり必ず不要ではなく、利益額や他の収入状況によって確定申告が必要になるケースもあることを理解しておくことが大切です。確定申告が必要となるケースを詳しく解説します。
年間20万円以上の雑所得がある場合
副業収入や不動産クラウドファンディングの分配金などは「雑所得」に区分されます。会社員の場合、この雑所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要とされています。しかし、年間20万円を超えると申告義務が生じ、住民税だけでなく所得税についても自ら確定申告を行わなければなりません。
特に注意したいのは、源泉徴収済みの投資収益であっても、20万円を超えると申告対象になる点です。「源泉徴収されているから安心」と思って放置すると、後で追徴課税や延滞税が発生するリスクがあります。少額なら不要ですが、利益が20万円を超えるかどうかはしっかり確認し、必要に応じて確定申告を行いましょう。
給与所得が2000万円以上の会社員
給与所得が2,000万円を超える会社員は年末調整の対象外となるため、匿名組合型の不動産クラウドファンディングで分配金が源泉徴収されていても、確定申告をしなければなりません。本来、匿名組合型では運営会社が20.42%を源泉徴収しているため、給与所得が2,000万円以下の会社員なら申告不要となる場合があります。
しかし、高額給与所得者にはこの特例が適用されず、給与と投資収益を合算して申告・納税を行うことが必要です。結果として、追加で納税が生じる場合や、逆に還付を受けられるケースもあります。投資による収益を含めて全体の税負担を把握するうえでも、確定申告は避けて通れません。
源泉徴収金額の一部の還付を受けたい場合
匿名組合型の不動産クラウドファンディングでは、分配金から一律20.42%の税金が源泉徴収されます。しかし実際の税負担は、投資家の所得状況や各種控除によって異なるため、人によっては源泉徴収された額が本来の納税額より多くなるケースがあります。
その場合は確定申告を行うことで、払いすぎた分の一部を還付してもらうことが可能です。特に医療費控除や扶養控除などを適用できる方、副業収入や他の投資損益と損益通算できる方は、税額が下がり還付を受けられる可能性があります。逆に、所得が多く税率が20%を超える場合には追加で納税が必要となるため、申告を通じて正確に精算することが大切です。
確定申告をしたら不動産クラウドファンディングの利用が会社にバレる?
不動産クラウドファンディングの収益を確定申告すると、会社に知られてしまうのではと不安に思う方もいます。結論から言いますと、住民税の通知方法や利益の金額によっては会社に伝わらないようにすることも可能です。ここでは、会社にバレることなく投資を続けられる方法についてご紹介します。
少額なら、変動する住民税の額は大きくは変わらない
不動産クラウドファンディングで得られる利益が少額であれば、確定申告によって住民税が多少変動しても、会社に気付かれる可能性は低いでしょう。最近は株式投資や副業、さらにはふるさと納税をきっかけに確定申告を行う会社員も増えており、住民税額が変わること自体は珍しいことではありません。
会社側も全社員の住民税額の細かい変動を逐一チェックしてなぜ増えたのかと詮索するほど余裕はなく、通常は総務や経理も深追いしないケースが大半です。そのため、投資による利益が年間数万円程度の範囲であれば、会社に不動産クラウドファンディングをしていることが伝わってしまうリスクは実際のところあまり心配しなくても良いといえます。
住民税を自分で納付(普通徴収)する形に変更するのも手
確定申告の際に「住民税は自分で納付(普通徴収)する」と選択すれば、投資による利益分が会社に通知されず、給与から天引きされる住民税にも反映されません。これにより、会社に不動産クラウドファンディングをしていることが伝わりにくくなります。
ただし、勤務先によっては「なぜ普通徴収にしたのか」と理由を聞かれる可能性もあるため、その点は注意が必要です。副業禁止規定を厳格に適用している会社では誤解を招くリスクもあるため、選択の際には職場の雰囲気やルールを踏まえて判断すると安心でしょう。少なくとも、納税方法を工夫することで会社に余計な心配を与えずに済む可能性が高まります。
年間利益20万円の範囲内で投資する
不動産クラウドファンディングの利益を年間20万円以内に抑えることで、確定申告が不要となる「雑所得の特例」を利用できます。給与所得者の場合、この範囲内であれば住民税や所得税への影響も小さく、会社に投資の事実が伝わるリスクもほとんどありません。
少額の運用であれば、税務上の手間も軽減でき、初めてクラウドファンディングに挑戦する方でも安心して取り組めます。ただし、20万円を超える利益が出ると申告義務が生じるため、年間の収益状況を定期的に確認することが大切です。利益を管理しながら少額ずつ投資を行うことで、税負担や会社への影響を最小限に抑えることができます。